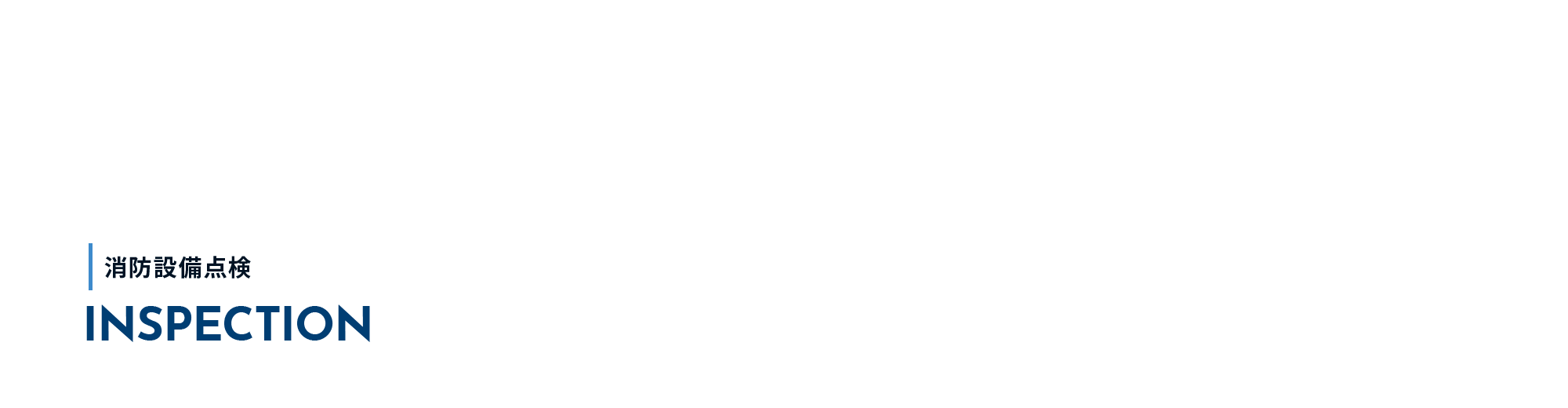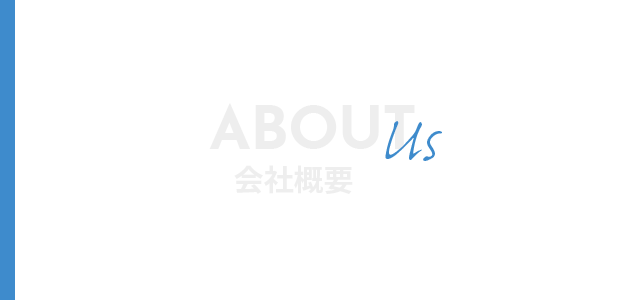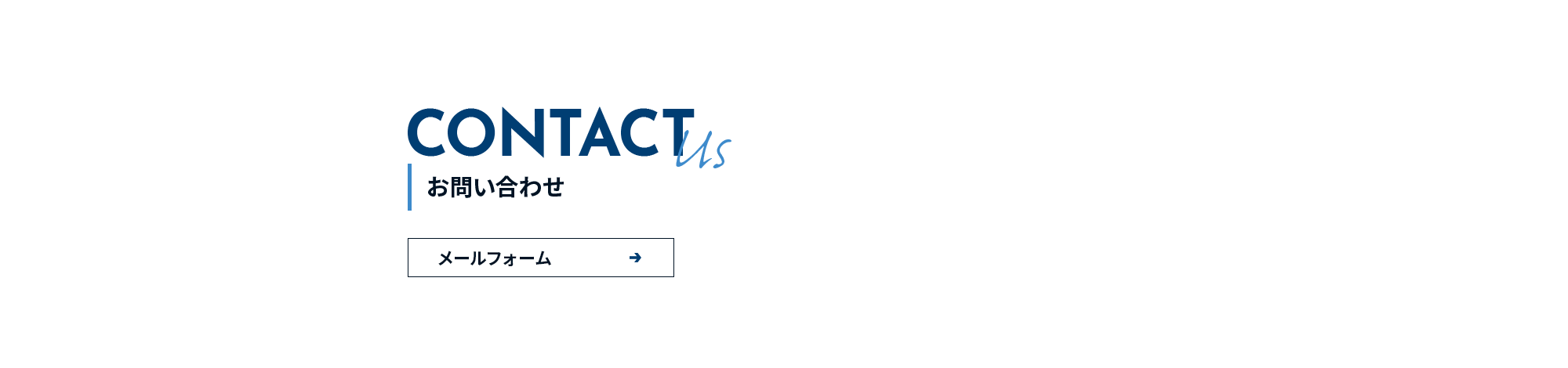消防設備点検なら徳原防災へ!
消防設備点検とは、建物に備え付けられている消防用設備が適切に維持・管理され、非常時の避難や初期消火を問題なく行えるかを点検する業務です。
徳原防災では、オフィス・公共施設・商業ビル・飲食店など、さまざまな施設での消防設備点検を行います。
建物の管理者には、定期的に消防用設備の点検を実施し、結果を消防署へ報告することが消防法によって定められています。

消防設備とは?
消防設備とは、消防法やその関係政令で規定する「消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設」の総称です。
警報設備・避難設備・消火設備・消防用水・消火活動上必要な施設があります。
〇警報設備
火災などが起きたことを感知し、警報・通報を発するための設備です。
自動火災報知器やガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器等がこれにあたります。
〇避難設備
火災などが発生したときに避難するために使われる機械器具や設備のことです。
避難はしご、誘導灯等です。
〇消火設備
火災が発生したときに水や消火剤を用いて消火を図る機械器具や設備のことです。
消火器をはじめ簡易消火用具、屋内消火栓設備、スプリンクラー等があります。
協力会社様:株式会社TPW
〇消防用水
防火水槽やこれに代わる貯水池、その他の用水のことです。火災発生時、消防隊による消火活動に用いられます。
〇消火活動上必要な施設
排煙設備や非常コンセント設備等、火災発生時に消防隊による消火活動に用いられる施設のことです。
これらの設備が不具合なく作動するかを確認することが、消防用設備点検のおもな内容です。
消防用設備点検の対象となる建物
〇延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
特定防火対象物とは、不特定多数の人が出入りする劇場、映画館、ナイトクラブ、飲食店、旅館、ホテル、病院、老人ホームなどのことを指します。
これらの建築物のうち、延べ面積(各階の床面積を合計した面積)が1,000㎡以上のものが、消防用設備点検の対象です。
〇延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定するもの
特定防火対象物に指定されていない建築物であっても、消防用設備点検の対象になる場合があります。
具体的には小学校、中学校、高等学校、図書館、博物館、美術館、神社、寺院、教会、工場などのことを指します。
これらは特定防火対象物ではないものの、地域の消防長・消防署長が必要と判断した場合、消防設備点検を行う義務が生じます。
〇屋内階段が一つのみの特定防火対象物
延べ面積が1,000㎡以下の特定防火対象物であっても、屋内階段が1つしかなく、1階・2階以外の階に「特定用途部分」がある建物は点検の義務があります。
特定用途部分とは、不特定多数の人が出入する場所が火災になった際に避難に支障をきたす部分のことです。遊技場、キャバレー、飲食店、物品販売店舗などが特定用途部分にあたります。
点検の種類
消防設備点検は、「総合点検」と「機器点検」の2種類があります。
また、消防設備点検は別に、「防火対象物点検」と「連結送水管耐圧試験」があります。
〇総合点検
消防設備の全部もしくは一部を作動させるか、当該設備を使用することにより、総合的な機能点検します。
たとえば、自動火災報知設備であれば感知器の感度試験をしたり、避難はしごであれば実際に降下して安全に使用できるかを確認します。
〇機器点検
消防設備の適正な配置、損傷などの有無、その他外観から判別できる事項、機能については外観から、または簡易な操作により判別できる事項を確認する点検です。以下の事項について確認をします。
・非常電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプの正常な作動
・機器の適正な配置、損傷等の有無その他外観から判別できる事項
・機能について、外観または簡易な操作により判別できる事項
〇防火対象物点検
応急措置や救援救護、避難誘導などの防火管理体制の点検です。
消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防火管理者によって消防計画に基づいて適切に行われているか、などが点検項目となります。
〇連結送水管耐圧試験
火災の際に消防隊が使用する連結送水管の点検・試験です。
高層ビルなどの連結送水管については、送水口本体や配管、接続部分や弁類などに変形・漏水などがないかをチェックすることが義務付けられています。
点検の頻度
消防設備点検をしたら点検結果報告書を作成し、消防署に報告書を提出する必要があります。ただし、報告の頻度と点検の頻度は異なっており、消防設備点検を行うたびに報告する必要はありません。
【点検の頻度】
〇総合点検
12ヶ月に1回以上。実際に消防設備を作動させ、総合的な機能を確認する。
〇機器点検
6ヶ月に1回以上。外観または簡易な操作によって消防設備を確認する。
【報告の頻度】
建物が特定防火対象物か否かで頻度はことなります。
〇特定防火対象物
1年に1回
〇非特定防火対象物
3年に1回
弊社が点検をしたあとは点検票に結果を記載して、建物の所有者・管理者・占有者に提出します。
建物の所有者・管理者・占有者は、点検結果報告書を消防署へ提出する必要があります。
点検の流れ
➀お問い合わせ、ご依頼
点検の時期が近づいてきたら、点検を依頼してください。
契約物件は前の月に弊社より日程調整のご連絡をします。
②消防設備点検
日程を決めて点検します。点検は消防設備士または消防設備点検有資格者のみが実施します。
③点検結果報告書を作成
弊社の点検担当者が作成します。
④管轄の消防署または消防出張所へ報告書を提出
特定防火対象物の場合は1年に1回、非特定防火対象物の場合は3年に1回、管轄の消防署または消防出張所に点検結果報告書を提出します。報告と同時に、防火対象物の維持台帳にも、点検結果を忘れずに記録しておきましょう。
※不備が認められた場合には、速やかに改修を行います。